UPDATE : 2014/Apr/03
AUTHOR:
コトバノイエ 加藤 博久
vol.03
少し長いけれど引用する。
体型は、羽根枕型。ふっくら焼き上がった切り餅の香りが立ちのぼりそうなすべっとさらっとした肌。髪はショートのチリチリパーマ。顔はすっぴん、なべて丸顔。眉薄く八の字、目小さい。お乳は小振りの滴型。ちょっと左右離れ気味だが、垂れ乳と称す程のボリュームはない。乳頭は色薄くこぢんまり。突起が低い(陥没かと思われる例多し)。尻は丸四角。写植でいうナールの趣。乾パンふたつ並べた景。ウエストが、ない。でも、膝から下が、秋刀魚のようにスリム。方々から寄せ集まったにしては、何故かくも如実に浅草体型が確立するのであろうか。オバチャンが一列に並んで、背中流しっこする様は、コアラのマーチさながらだ。ぱくり一口頬張りたい位、愛くるしい。(饗の四 東京浅草「蛇骨湯」)
女体は、炊きたてコシヒカリ。つやつやぷりぷり、湯を珠と弾く。急傾斜なで肩、下半身なすび型ぽってり充実。乳輪大きく、新竹の子の腰周りに似、堅そうに赤みを帯びて、くっきり粒立つ。乳頭小豆大。ネルドリップ袋型垂れ乳。後姿、掛け軸の裏の如し、偏平尻。陰毛薄し、ぱやぱやと間引かれたアルファルファ。下腹のボリュームに比し、肢はしんなり華奢。ことに足首から下は、子供並に小さい。にんにくの皮を剥いたような、くるりんとした踵。鞘から弾ける枝豆の指五本。掌にすっぽり入る、表面吉野葛仕立ての練り切り、初夏の茶菓の趣。纏足を想う。裸足フェチなら、即座に脊髄へ電流が疾るだろう。(饗の七 新潟県関川村「上関共同浴場」)
わし(わしとおぬしのわし)こと、杉浦日向子さんの銭湯めぐりの一節。
尻は写植のナールとか、乳輪はブランデーグラスの脚底部のサークルサイズとか、陰毛薄し、ぱやぱやと間引かれたアルファルファとか、女のひとが生の女体を描写すること自体けっこう珍しいことだけれど、こんな表現みたことない。
まさに metaphor の力。

□ 入浴の女王 | 杉浦日向子 | 講談社 | 1995
面白い、ひたすら新鮮、なにげなく読みはじめたら止まらない。
著者は、2005年に若くして亡くなった女流漫画家・江戸風俗研究家、そしてあの荒俣宏の元奥さん。
名前はもちろん知っていたけれど、この人の本を買うのは初めてで、タイトルと、それに呼応するようなご本人の手になるジャケットのイラストのなまめかしさに惹かれておもわず手にとった。
「舞妓さんの、おっぱい。」
こんな書きだしではじまる銭湯巡り**は、やはりチャーミングとしか言いようがない。
子供のころ友だちと待ち合わせた銭湯で(置き道具して毎日銭湯に通ってる友だちがうらやましかった)、番台のおばちゃんにお金を渡すときのあのワクワク感や、湯上がりに、専用のピンでビニールごと紙の蓋をはがして飲むコーヒー牛乳のうまさ、そして学生のころ通った京都寺町の鄙びた銭湯の湯気の匂いや、はじめて入った東京の銭湯の信じられないあの熱さ。
この本を読んでいると、身体に残っているさまざまな銭湯(関西では風呂屋といったほうが気分かもしれない)の記憶が、リアルによみがえってくる。
銭湯はいいョ、女湯じゃなくても。
キッチュなタイル絵、ケロリンの黄色い湯桶、今にも壊れそうな籐の椅子、坪庭の池にいる鯉、ちょっと古ぼけた扇風機、大きなカンカン、木の鍵がついた下足箱。
すべてのパーツが、小ざかしい計算を越えて、一心不乱に、入浴という悦楽にむかってる。
人間の行為でおもわず極楽昇天ボイスがでるのは、飲食と性交、そして入浴だけかもしれないと、ふと思う。
「まず、行って、全身で、その地を味わってみさんせえ。理屈じゃねえ。言葉じゃねえ。湯から肌へ、おもいがつたわる。頭じゃねえ。小手先じゃねえ。毛穴が知る情報がある。」

銭湯を貧乏臭いものに貶めたのは、「神田川」のちっぽけなセンチメンタリズムじゃないかと思うけれど、1958年生まれのフォーク世代の人が、こうやって豪快に快楽装置としての銭湯を、ノスタルジイではなくリアルタイムのものとして、しかも小賢しい理屈じゃなくフィジカルなものとして語っているのは、なんとも爽快だ。
世の中のあれこれには、いろんなモノサシがあるけれど、生きている人間にとっては、快楽原則こそが、もっともナチュラルな行動原理なんだから、まずは自分にとって気持ちいいコトを考えることからしか、明るい未来ははじまらないだろう。
快適じゃなければ、地球なんてなくなったっていいとさえ思う。
「極楽は、ちょっと手を伸ばせば届くとこにある。地獄は、うっかりよろけるその足下にある」
足下にある地獄は、どこへいっても無くなるものじゃないから、ちょっと手を伸ばして極楽のドアをひとつずつ開けていくしかないよね、よろけないように。
こういうけっして隠棲したり出家したり純文学したりしないfunkyな女流作家は(「若隠居」という自称は、持病との闘い**をカムフラージュする、いかにも江戸っ子的なシャイネスだったようだ)、日本では稀有なだけに、夭折がとても惜しい。
ファンの間ではすでに傑作として名高いという、「百物語」と「百日紅」を、さっそく手配した。
でもまずは、ひとっ風呂。
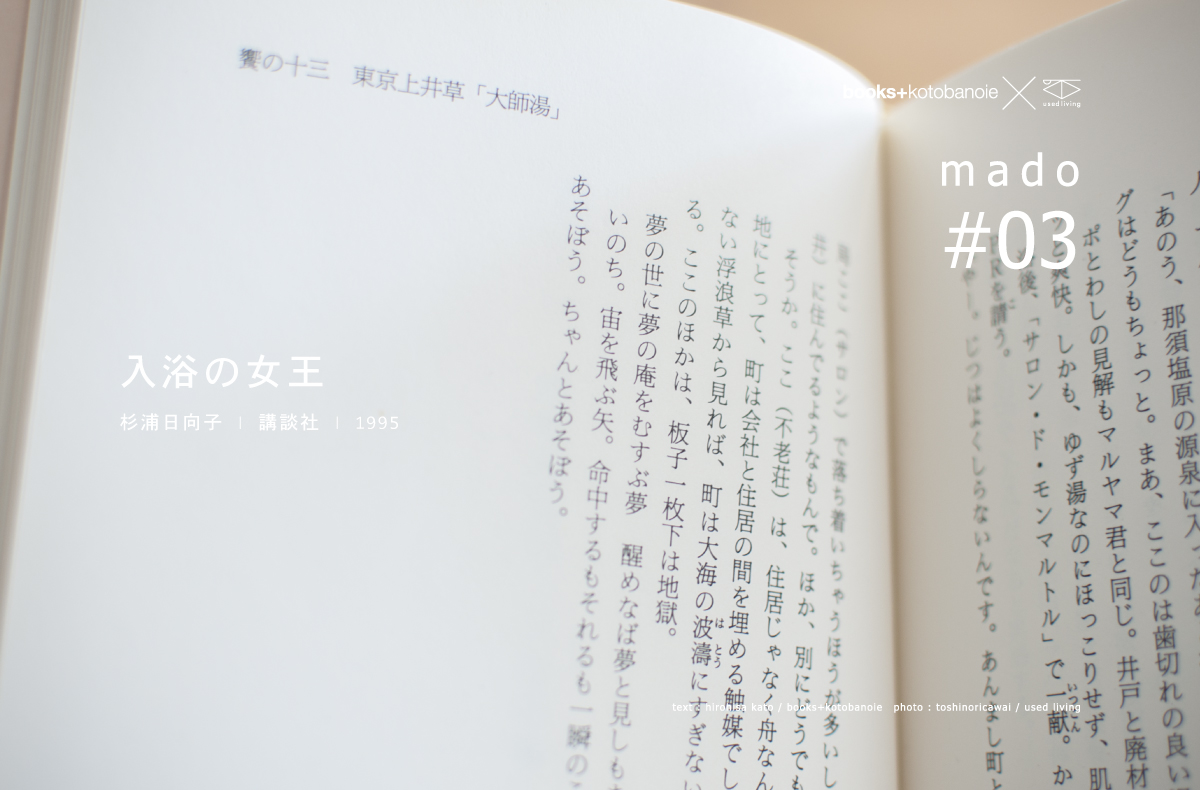
++++++++++++++++++++++++
脚注1「銭湯巡り」
饗の一 銀座「金春湯」
饗の二 石川金沢「東湯」
饗の三 四条木屋町「明石湯」
饗の四 東京浅草「蛇骨湯」
饗の五 名古屋「三越湯」
饗の六 戸越銀座「中の湯」
饗の七 新潟関川村「上関共同浴場」
饗の八 山形・群馬「駅即銭湯」
饗の九 東京上野「燕湯」
饗の十 東京三鷹「三鷹湯」
饗の十一 横浜山手「さくら湯」
饗の十二 代官山同潤会内「文化湯」
饗の十三 東京上井草「大師湯」
饗の十四 東京早稲田「美松浴場」
饗の十五 大阪生野区「源ケ橋温泉」
初出は『小説現代』
1994年1月から1995年3月にかけて、この15の銭湯を、「われこそは入浴の女王也」と豪語するわし(著者)と、「ポアール・ムースM」と名づけられた入浴の王女(担当の女性編集者)が巡るこの女湯紀行は、その銭湯がある地域のキーパーソン(男性)たちとの湯上がりの一献を愉しむという趣向もあって、「銭湯に入れば、その湯気の向うに、包み隠さぬその町の素顔が、まるごと見えてくる」という地域文化論にもなっているのが、いかにも文芸誌の連載らしいところかな。
脚注2「持病との闘い」
「先に死んだら、経をあげてやると約束した男が、金沢にいる。中略 それが実現すりゃ、つまらない死も、なんぼかおもしろく取り繕ってくれるだろうと、のびる餅を苦しく飲み込みながら、ちょっぴり愉快だった。」
「なるほど、うまれかわるのなら、トンボも悪くない。人間は一度やったから、つぎはモウいい。」
「いのち。宙を飛ぶ矢。命中するもそれるも一瞬のこと。ともあれいまは飛んでいる。だから、あそぼう。ちゃんとあそぼう。」
この銭湯記でも、こんな風に忍び寄る死の陰を感じさせる記述がところどころにあって、ちょっと沁みる。
